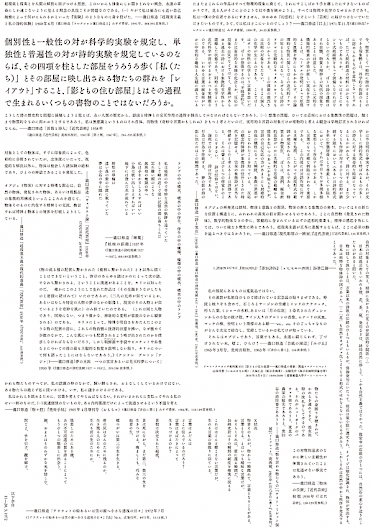個別性と一般性の対が科学的実験を規定し、単独性と普遍性の対が詩的実験を規定しているのならば、その四項を柱とした部屋をうろうろ歩く「私(たち)」とその部屋に映し出される物たちの群れを「レイアウト」すること、「影どもの住む部屋」とはその過程で生まれるいくつもの書物のことではないだろうか。
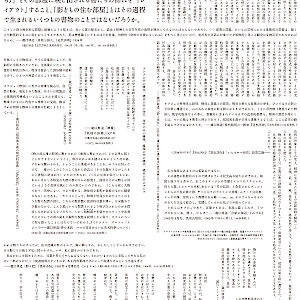
山本浩貴(いぬのせなか座)-久保仁志(展示企画者)-山腰亮介(展示企画特別協力者)
2018年3月9日|18:00-20:00|慶應義塾大学アート・スペース
こちらからダウンロードして下さい。
制作:山本浩貴(いぬのせなか座)
超現実と現実とを人間の解放に結びつける思想、このいかにも抽象にしか聞きとれない概念、永遠の革命にしか通じないように見える理念の具現こそが問題なのである。〔…〕やがて私は暴力にも近い自己抛棄によって何がえられるかといった『実験』のようなものに身を投げた。――瀧口修造「超現実主義と私の詩的体験」1960年6月(瀧口修造『コレクション瀧口修造1』みすず書房、1991年、388-391頁参照。)
たまたまこれらの作品はすべて物理的現象に乗じて、それにすこしばかり手を藉したにすぎないものばかりです。見る人がそこにどのような幻や像を眺めようと、すべては物理や化学のなせるわざであり、私は一個の介在者であるにすぎません。ゆめゆめ「幻想的」なぞという「芸術」に結びつけないでいただきたいものです。さて、では私はどこにいるのでしょう?――瀧口修造「口上」1971年11月(瀧口修造『コレクション瀧口修造5』みすず書房、1994年、34-35頁参照。)
今、物質として一般的に指示することのできる現象體とは、科学的な假説のもとに認められるものを意味しないとすれば、ただ人間的創造の材料にほかならないものであろうか。 あるいはそこにカント式絶縁體をもって装備しなければならないのだろうか。 ぼくは詩の運動はそれ自體、物質と精神との反抗の現象であることに注意した。 しかし二元的な機能的要素の矛盾が新しい実在を予想することは、ヘーゲルの発明によって原理的な眞理を得たにもかかわらず、その論理的な性質に関してはこの近代的ドラマの知るところではない。なぜならば詩のドラマは先験的なキャタストローフをもたないからである。 この演劇の激烈さは比較の対象をもたない。 そこに個人の化学が生じるのである。 ここでぼくはポーの知性の化学という言葉を想いだす。 ぼくが想像するのは、不随意的な、または盲目的な本能の化合とか、反応の現象やH2Oなどではなく、意識があらゆる過去の詩における象徴的文学性から遊離した状態であり、同時に化学という近代科学が啓示するおそるべき実験劇なのである。 いわゆる言葉の練金術がいかに中世的な趣味と人生観に満ちているかは今日明白な事実であるが、それが文学とくに詩的形式と呼ばれるものの多くの詩人に対する致命的な陥穽になっているにもかかわらず、詩に対する、また少なくとも作詩に対するひとつの信仰が継続する限りにおいて(あるいは詩的形式を単に世襲財産として尊重している限りにおいて)、それは今日もなお多種多様な変形として存在するのである。 しかし言葉のもつ正確な制限はきわめて重要である。 この内部には言語作用に対する正確な処理、したがって表現形式の範囲が規定されるだろうからである。 特質ある物質狂。 ぼくは、通例、練金術的思想がいかに先験的な思惟の範疇から関係を失いつつあったかを知らないが、言語の自己反応の力があまりにも封建的自我の犠牲になった瞬間、象徴の罪悪がおこなわれたことを知っている。 反応の観念的倒錯が象徴詩の佳什とされた時代を記憶せよ。 完全の象徴詩が正当な情緒をのこしたと考えることは誤謬である。 それは譬えばひとつの痒覚をのこしたにすぎない。 詩は信仰ではない。 論理ではない。 詩は行為である。 行為は行為を拒絶する。 夢の影が詩の影に似たのはこの瞬間であった。――瀧口修造「詩と実在」1931年(瀧口修造『瀧口修造の詩的実験1927〜1937』思潮社、1967年、226-229頁参照。)
こうした詩の歴史的な問題に接触しようと思えば、永い人類の歴史から、語法と精神との交互作用の過程を摘出してみなければならないであろう。〔…〕想像の問題、ひいては芸術における象徴性の問題は、飽くまで物質的なものに向かおうとするであろう。私は無意識というものはそれ自体、向物性(奇妙な言葉かもしれぬ)をもつと考えたいのだ。実用的な言語の対象だけが唯物的と考える観念は早晩訂正されなければならぬ。――瀧口修造「貝殻と詩人」『近代芸術』1938年(瀧口修造『近代芸術』美術出版社、1962年[第2版、1967年]、204 -205頁参照。)
オブジェの再発見は結局、物体と意識との関係、物体の新たな象徴力の発生、ひいてはその新たな位置と構造とに、われわれの真実の目を開かせるものであろう。ことに自然物(発見された物体)、数学的物体などの中に、客観的に含まれているはずの造形的要素も、精神の感応を外にしては、ついに縁なき衆生に終るであろう。超現実主義が正当に進展するならば、ここに必至の路を辿るべきではなかろうか。――瀧口修造「現代彫刻の一断面」『近代芸術』(『近代芸術』、134頁参照。)
自然の対象としての花と、精神に生かされた花との弁証法的な関係〔…〕
日本の結晶芸術といわれる能、花、茶、庭、発句などは、結局自然に即して、しかも自然主義ではなかった。龍安寺の石庭のひとつには、自然石の重心を逆さにしたものがあると聞いた。
物に則して詠むことは、万葉以来の詩歌の伝統のひとつともいえるが、俳諧発句にいたって、叙述は最小限に還元され、イメージは順化強調され、物体が突出する。
日本は独特な物体詩の国であった。〔…〕「花」も自然をオブジェ化しようとする形式にほかならないといえるであろう。しかしそれは自然の中から秩序を発見することであった。――瀧口修造「狂花とオブジェ」『近代芸術』(『近代芸術』、218-219頁参照。)
かれら物たちのすべてが、私の認識の枠のなかで、飼い馴らされ、おとなしくしているわけではない。ある物たちは絶えず私に問いかける。いや、私に謎をかけるのである。
私はかれらを鎮めるために、言葉を考えてやらねばならない。それがいまかれらに支払ってやれる私のせい一杯のものだ。〔…〕流通価値のないものを、ある内的要請だけによって流通させるという不逞な考え――瀧口修造「物々控」『美術手帖』1965年4月増刊号〈おもちゃ〉(瀧口修造『余白に書く』みすず書房、1966年、118-119頁参照。)
物たちの身振りを聴きわけ、かれらを連れてきて、彼女独特の洗礼をしてやるのである。それがニューヨークのバウァリ街であろうと、東北の農家の庭先であろうと、世田谷の消防署であろうと――瀧口修造「物を言わぬ物たちの」『ケイト・ミレット個展』[リーフレット]、南画廊、1963年4月(『余白に書く』、60頁参照。)
対象としての物体は、すでに印象派によって、色彩的に分割されていたが、立体派にいたって、視覚的な解決以外に、物体は複合した諸体験の総和であり、ひとつの神話であることを発見した。――瀧口修造「キュビスム論」『近代芸術』(『近代芸術』、28頁参照。)
オブジェ(物体)に対する特殊な関心は、自然の物体、発見された物体、あるいは既製品の象徴的再構成といったこころみを通じて、物体そのものに内在する精神との交流、換言すれば精神と物体との境界を打破しようとしている。――瀧口修造「超現実主義の現代的意義」『近代芸術』1938年(『近代芸術』、165頁参照。)
ランプの中の噴水、噴水の中の仔牛、仔牛の中の蠟燭、蠟燭の中の噴水、噴水の中のランプ
私は寝床の中で奇妙な昆虫の軌跡を追っていた
そして瞼の近くで深い記憶の淵に落ちこんだ
忘れ難い顔のような
眞珠母の地獄の中へ
私は手をかざしさえすればいい
小鳥は歌い出しさえすればいい
地下には澄んだ水が流れている
卵形の車輪は
遠い森の紫の小筐に眠っていた
夢は小石の中に隠れた
――瀧口修造「睡魔」『妖精の距離』1937年(『瀧口修造の詩的実験1927〜1937』、188-189頁参照。)
《物の或る種の配置に驚かされた(最初に驚かされた)とき以外に描くことはできないということ、啓示のあらゆる謎はかれにとって次の語、すなわち驚かされる、ということに関連があることを、キリコは知ったのだ。 確かにこのようにして生れた作品は〈その生誕をうながしたものと密接に結ばれて〉いたのであるが、〈二人の兄弟が似ているとか、あるいはむしろ特定の人物の夢のなかの影像と、現実のその人物とが似ているような奇妙な風に〉のみ似ていたのである。 〈これは同じ人物であり、同時にない、つまり微かな、神秘的な変形が容貌のなかに観察される〉のである。 キリコにとって、特殊な明白さをあたえたこのような物の配置の前に、これらの物自體に批評的注意を拂い、なぜ極めて少数のなかで、こんな風にいつも配置されるよう喚び出されたのかを探求しなければならないだろう。しかし朝鮮薊〔アルティショ〕や手袋やビスケットや糸巻などについての彼の最も主観的な視覚を説明しない限り、キリコについて何も語ったことにはならないであろう。》(アンドレ ブルトン「ナジァ」)――瀧口修造「夢の王族 一つの宣言あるいは先天的夢について」1930年(『瀧口修造の詩的実験1927〜1937』、205-206頁参照。)
私の部屋にあるものは蒐集品ではない。
その連想が私独自のもので結ばれている記念品の貼りまぜである。時間と埃りをも含めて。石ころとサージンの空鑵とインドのテラコッタ、朽ちた葉、ミショーの水彩、あるいは「月の伝説」と命名されたデュシャンからの小包の抜け殻、サイン入りのブルトンの肖像、ムナーリの灰血、マッチの棒、宏明という商標のある錐……etc.,etc. そのごっちゃなものがどんな次元で結合し、交錯しているかは私だけが知っている。
それらはオブジェであり、言葉でもある。永遠に綴じられず、丁づけされない本。壁よ、ひらけ!――瀧口修造「白紙の周辺」『みづゑ』1963年3月号、美術出版社、1963年(『余白に書く』、116頁参照。)
この対物的追求のなかに新しい主観性が準備されていたことは見逃せない事実であろう。――瀧口修造「物体の位置」『近代芸術』初版1938年(『近代芸術』、138-139頁参照。)
X状況
物資そのものが、物から一瞬離れて、言葉となることがある。
言葉となる、とはいつも曖昧な言葉だが、
おそらくそれは、質に還る瞬間だ。
加納光於はその瞬間の純度を確実に捉える
これはほとんど聴こえない言葉だが、
生れる言葉の身振りに似ている。
言葉はふだんは
どこに住んでいるのだろう?
言葉はまばたきによって
生きつづけるのか?
貝殻は決定された組成。
貝は死にながら、まだ第二、第三の生を
生きつづける。痛ましくも、巧みな
他者の生。
蝶つがいは第三の生を生きる。
骨の灰はなんのために残るのか。
生き残る人のためにか、
生れる前の生のためにか、
眼差しのためにある鏡、
あの不可浸透の質を潜ることによって
もうひとつの眼差しに出会う。
銅、おまえはそのわずかな光を惜しむ。
閉じよ、手を引け、纜を解け。
以下余白
11—20,3,1972
――瀧口修造「アララットの船あるいは空の蜜へ小さな透視の日々」1972年7月(「アララットの船あるいは空の蜜へ小さな透視の日々」『点』No.4、点発行所、1972年、11-13頁。)
Date
Friday 9th March 18:00-20:00
Venue
Keio University Art Space
Audience
Everyone welcome
Cost
Free participation
Enquiries and bookings
Keio University Art Center
+81-3-5427-1621
pj.ca.oiek.tsda@ijnet-ca
Gallery talk[Introduction to Archives]
Date
Friday 9th March 18:00-20:00
Venue
Keio University Art Space
[Located on the ground floor of Keio University South Annex]
2-15-45, Mita, Minato-ku, Tokyo, 108-8345
Tel. 03-5427-1621 Fax. 03-5427-1620
JR: Tamachi station on Yamanote - and KeihinTohoku Line
Subway: Mita station on Mita Line, Akabanebashi station on Oedo Line
Audience
Everyone welcome
Cost
Free participation
Enquiries and bookings
Keio University Art Center
+81-3-5427-1621
pj.ca.oiek.tsda@ijnet-ca
Organiser(s)
Organiser: Keio University Art Center
Grant: The Kao Foundation for Arts and Sciences
Review:「個別性と一般性の対が科学的実験を規定し、単独性と普遍性の対が詩的実験を規定しているのならば、その四項を柱とした部屋をうろうろ歩く「私(たち)」とその部屋に映し出される物たちの群れを「レイアウト」すること、「影どもの住む部屋」とはその過程で生まれるいくつもの書物のことではないだろうか。」の余白に
一冊の書物を制作することをひとつの行為としてとらえたとき、その制作プロセスには、その行為を構成する細分化された無数の「行為」が折りたたまれている。そのようなが折りたたまれた行為がひらかれることを待っている書物を、私たちは一冊知っている。
瀧口修造の『余白に書く』(みすず書房、1966年)は、書斎あるいは制作の場が中心的なモチーフであり、まさに「一冊の書斎」とも云える書斎の模型であった。「余白」とは、書物の欄外にある文字通りの余白でもあるが、それだけではない。制作という行為の周辺にある場所、すなわち書斎もまた「余白」として捉えることができる。書斎とは、制作プロセスの中で様々な思考や記憶が縦横無尽に飛び交う場所すなわち「影ども」の住む部屋である。この展示を見る私たちは、出展された書斎写真(これも書斎の「影ども」のひとつであろう)を通して、1953年から1979年に至るまでに瀧口が繰り返し行った部屋のレイアウト(布置)の編集に気づくとともに、1955年から1965年に書かれたテクストのアンソロジーである『余白に書く』に注目し、その初出資料群に掲載されたテクストと『余白に書く』で再録されたテクストを比較することで、それぞれ異なる出自を持つテクスト群が一冊の本として結晶化する際の編集の手続きの一端をたどることができた。そして、この展覧会自体もまた、『余白に書く』という書物の模型として「読まれる」ことを意図していた。『余白に書く』が一冊の書斎として捉えられるように、この展覧会自体を「一室の書物」と捉えることも可能であろう。さらに展示の模型として作られた展覧会カタログは、展示空間を紙面上のレイアウトで再現を試みる、いわば「一冊の部屋」でもあった。
トークでは、瀧口修造の書斎写真や『余白に書く』とその初出資料群のそのような性質を指摘するだけではなく、企画者である久保氏、展覧会のポスター・DM・カタログをデザインした「いぬのせなか座」の山本浩貴氏、そして本展に特別協力した私の三名が、瀧口修造の諸資料を、それらを公開する展示を、展示自体の模型でもあるような印刷物を、編集・制作したプロセスについて語った。
その一端を紹介しよう。久保氏は、自らが本展のために執筆したリード文が、山本浩貴+h氏の二人によってポスター内に改行などを伴ってレイアウトされたことで、テクストの構造があらわになり、編集・書き換えを促されたと語った。山本氏からはポスターについて企画側から提示された注文、具体的には、出展資料のなかのどれかひとつをピックアップするようなデザインにはしないこと、『余白に書く』の初出資料群のリストを掲載することなどに応えるなかでレイアウトが決まったことが語られ、企画者側とデザイナー、双方向の働きかけによって制作された過程があきらかにされた。展示のレイアウトも同様で、キャプションや出展資料の配置の一部にカタログのレイアウトからのフィードバックがあり、展示とカタログは必ずしもどちらかに従属するものではなく、相互に関係しあい、構築されていったことが語られた。
また、カタログに収録された久保氏と私のテクストのそれぞれに挿入された、一見すると同じもののように見える二つの図版の微妙な差異が、レイアウトによってより明示的になった例についても話題にのぼった。レイアウトなどの形式と、テクストをはじめとした内容を一致させようというモチーフが本展の随所で見られるが、本展の印刷物に施されたレイアウトは、かならずしもその一致において絶対的なものではないことも言及された。私たちのテクストやレイアウトは、制作の過程で何度もその姿を変えていき、それぞれの判断でカタログとして結晶化したテクスト・レイアウトも、今後変化する可能性があることが示唆された。
山本氏は『余白に書く』の掲載された「白紙の周辺」のなかで「私だけが知っている」というときの、「私」とは誰か、とトークで問うた。編集がおこなわれている過程で、さまざまな「私」がそのときどきに現れ、その「私」とはいつ、どの時点での瀧口という個人に還元されるのだろうか。「白紙の周辺」は雑誌『みずゑ』(1963年)に発表されたが、『余白に書く』に収録されたときに大幅な変更が為されている。編集の過程でそのつど立ち現れる「私」の「影」はひとつではなく「影ども」であり、複数化している。久保氏がトークのなかで語ったように、私たち四人の共同制作は、アイディアの提案は各々から発せられたもので、テクストやレイアウトの最終的な決定は各々が為したものではあるものの、その編集過程では各々のアイディアが混ざりあい、その境界があいまいになるものであった。編集のなかではいくつもの「私(たち)」が立ち上がってくるのだ。
イベントでは、山本浩貴+h氏が制作した瀧口修造のテクストのアンソロジーが配布された。このアンソロジーはそのレイアウトによって、まるで部屋をうろうろと歩くかのような感覚を読者に与え、まるで「丁づけされない本」(「白紙の周辺」)のように機能し、終りがないかのようにも読めると久保氏は指摘する。瀧口自身の言葉によって語られるこの瀧口論として読めるこのアンソロジーは、レイアウトがテクストの持つポテンシャルを引き出すひとつの方法であることを示しているといえるだろう。
このトークのタイトルは、瀧口修造の「詩と実在」(1931年)が念頭に置かれてつけられた。それについて久保氏からつぎのように説明された。「詩的」実験と「科学的」実験は異なるものであり、「科学的」実験で抽出されるもの(たとえば実験室でNaClのような元素記号に置き換えられる「純粋な」塩のように)は交換・再現可能な一般性を持ち、不純な要素が取り払われた個別的な「もの」である。一方で「詩的」実験は、「科学的」実験では排除されてしまう、一般化を拒むもの、すなわち再現不可能な不純物を含んだ単独的なものでありながらも、普遍性を持つもの(読まれうるもの)といえるだろう。それに応じて山本氏は、ある特定の個人である「私」に還元されない「私(たち)」を考えるときに、瀧口が『近代芸術』(初版1938年)から考えていた「オブジェ」の問題が立ち上がってくるのでは、と問題提起し、久保氏との掛け合いが生まれた。「オブジェ」とはコンテクストから切り離されたものと定義することができる。だが、コンテクストから逃れることは難しい。仮にコンテクストから逃れ去るものがあるとしたら、むしろ不純物が前景化した「もの」であり、「オブジェ」とは単独性と一般性を同時に備えたあわいのものではないだろうか。瀧口修造は、制作が続く限りあり続ける生とはなにかを、「オブジェ」を操作し、編集し続けたことで問い続けていた人物であった、とひとつ結論づけることができるだろう。
本展で「私(たち)」が編集・レイアウトしたこの展覧会も、上述のような持続のなかで制作されたと考えることができるだろう。そして、ある対象を研究すること、また展覧会として提示することは、あらたにレイアウトを施すことに他ならない。この展覧会を通して「私(たち)」が提示した方法は、瀧口の提示した「影どもの部屋」とは、別のものであろう。ものをレイアウトすること、すなわち部屋をうろうろ歩くことで、瀧口自身が書斎のレイアウトの改変によってその都度に別の書斎を提示して見せたように、また初出形体から編集を介して『余白に書く』が一冊の書物として結晶化した後もさらに編集を施されたように、「影どもの住む部屋」はいくつもの「書物」として生まれ、これからも生まれることになるのではないだろうか。